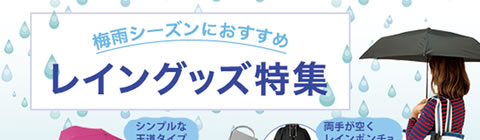販促レポート
2019/03/18 専門家の解説
ウェブ担当さん必見!読みやすい企業ブログを書く方法/おれじなる
もっと読みやすいブログ記事を書きたい!そんな願望を持つ広報担当さんウェブ担当さんも多いはず。魅力的で読みやすい文章は「読み返し→校正」の繰り返しが必要ですが、本日はそれらを効率よく実践する方法をご紹介します。
記事の読みやすさは「読み返し」で決まる

広報販促など、今や会社の重要セクションを担う企業ブログ。それらのエンジンは、やはり何と言ってもコンテンツ。本日は、読みやすい企業ブログを書く方法の考察です。
早速、コンテンツ記事を書く工程について整理してみましょう。コンテンツ執筆時は、大きく分けて以下の5つの工程に分類されます。
特に「読み返し」は、「記事の校正」の工程において大切な作業になります。
書くことに慣れていない人は、「記事の執筆」と同時並行で表現の「言い回し」や「体裁」も考えてしまいがちですが、しかしこのスタイルだと、記事の仕上がりが遅くなるし表現も冗長になりがちです。
執筆時はできるだけ伝えたい「内容の盛り込み」に専念し、細かな表現や言い回しは「読み返し→校正」でまとめて実践すると、効率よく統一感のある企業ブログに仕上げられます。
この「読み返し→校正」プロセスへの「こだわり」こそが、コンテンツ品質のカギとなりますので、ぜひ注目してください。
読みにくいブログ記事の特徴

読みやすい記事を書くには、「読み返し→校正」が重要という話をしましたが、改めて読みにくいブログ記事とはどういうものか説明します。以下にポイントにしてまとめてみました。
比喩表現を多用している
「~のような」「~のごとく」の多用。形容詞や比喩表現は、難しくイメージできないものを簡単に置き換える時に使うのですが、読みにくい記事では、これが多用されていて何を言いたいのか良く分からない状態になっています。
能動態と受動態が混ざっている
一つの言い回しでも、能動態では「みんなから応援される人」、受動態では「みんなが応援する人」と言うことができます。どちらも正解ですが、能動態と受動態が混じっていると、読み手は混乱し、内容を理解しにくくなります。
専門用語を多用している
企業ブログの場合、訴求するターゲットによって、ある程度の専門用語が求められます。一方で、専門用語の多用は、読み手を混乱させる原因になります。専門用語と平易な言葉とのバランスがコンテンツ作成に求められます。
読みやすい企業ブログを書く方法

読み返しをする際に気を付けるべきポイントを考察してみました。ただ読み流すのではなく、下記を特に注意し「読み返し→校正」に役立ててください。
誤字脱字や表現の間違いを確認する
まず、誤字脱字を一通りチェックしましょう。他にも、漢字だと読みにくい文字、間違った表記の固有名詞(例:IPhONEなど)、間違った使い方をしている慣用句・四字熟語などもあわせて確認するとベターです。
前後のつながりをチェックする
1段目と2段目のつながりは自然か?脈絡なく文章がはじまっていないか?前後の繋がりをくまなく確認しましょう。また内容が前後で矛盾していないかもチェックしましょう。つながりが不自然だと、読んでいてつまずく原因になります。
テーマの深度を確認する
ここでは、テーマに対して深く適切に考察できているか確認します。表面的な内容で読者にとっては面白みのない内容になっていたり、考察が足りていないと感じた場合は、根拠となる調査データや自身の視点を付け加えていきます。
語尾や言い回しを確認する
読みやすさに最も影響するポイントで、「もっと簡単な言い回しや表現」を探りながら読むと効果的です。読みやすさに最も大切な「簡潔さ」、この視点を持ち精査することで、魅力的で読みやすい文章に近づけられます。
首尾一貫しているか確認する
最後は記事全体がテーマに矛盾していないかを確認します。タイトル、サマリ、本文、まとめ内容の一貫性、起承転結は正しく構成されているかを見ます。このプロセスを妥協なく突き詰めることで更に読みやすい文章となります。
読みやすい文章を作るのに、言葉のセンスはさほど重要ではありません。最後のツメの作業である「読み返し」で、読み手の立場に立ったわかり易い表現に変えられるかがキモです。是非参考にしてみてください。
<ライタープロフィール>

広報販促など、今や会社の重要セクションを担う企業ブログ。それらのエンジンは、やはり何と言ってもコンテンツ。本日は、読みやすい企業ブログを書く方法の考察です。
早速、コンテンツ記事を書く工程について整理してみましょう。コンテンツ執筆時は、大きく分けて以下の5つの工程に分類されます。
- 構成案の作成
- 取材と調査
- 記事の執筆
- 読み返し
- 記事の校正
特に「読み返し」は、「記事の校正」の工程において大切な作業になります。
書くことに慣れていない人は、「記事の執筆」と同時並行で表現の「言い回し」や「体裁」も考えてしまいがちですが、しかしこのスタイルだと、記事の仕上がりが遅くなるし表現も冗長になりがちです。
執筆時はできるだけ伝えたい「内容の盛り込み」に専念し、細かな表現や言い回しは「読み返し→校正」でまとめて実践すると、効率よく統一感のある企業ブログに仕上げられます。
この「読み返し→校正」プロセスへの「こだわり」こそが、コンテンツ品質のカギとなりますので、ぜひ注目してください。
読みにくいブログ記事の特徴

読みやすい記事を書くには、「読み返し→校正」が重要という話をしましたが、改めて読みにくいブログ記事とはどういうものか説明します。以下にポイントにしてまとめてみました。
比喩表現を多用している
「~のような」「~のごとく」の多用。形容詞や比喩表現は、難しくイメージできないものを簡単に置き換える時に使うのですが、読みにくい記事では、これが多用されていて何を言いたいのか良く分からない状態になっています。
能動態と受動態が混ざっている
一つの言い回しでも、能動態では「みんなから応援される人」、受動態では「みんなが応援する人」と言うことができます。どちらも正解ですが、能動態と受動態が混じっていると、読み手は混乱し、内容を理解しにくくなります。
専門用語を多用している
企業ブログの場合、訴求するターゲットによって、ある程度の専門用語が求められます。一方で、専門用語の多用は、読み手を混乱させる原因になります。専門用語と平易な言葉とのバランスがコンテンツ作成に求められます。
読みやすい企業ブログを書く方法

読み返しをする際に気を付けるべきポイントを考察してみました。ただ読み流すのではなく、下記を特に注意し「読み返し→校正」に役立ててください。
誤字脱字や表現の間違いを確認する
まず、誤字脱字を一通りチェックしましょう。他にも、漢字だと読みにくい文字、間違った表記の固有名詞(例:IPhONEなど)、間違った使い方をしている慣用句・四字熟語などもあわせて確認するとベターです。
前後のつながりをチェックする
1段目と2段目のつながりは自然か?脈絡なく文章がはじまっていないか?前後の繋がりをくまなく確認しましょう。また内容が前後で矛盾していないかもチェックしましょう。つながりが不自然だと、読んでいてつまずく原因になります。
テーマの深度を確認する
ここでは、テーマに対して深く適切に考察できているか確認します。表面的な内容で読者にとっては面白みのない内容になっていたり、考察が足りていないと感じた場合は、根拠となる調査データや自身の視点を付け加えていきます。
語尾や言い回しを確認する
読みやすさに最も影響するポイントで、「もっと簡単な言い回しや表現」を探りながら読むと効果的です。読みやすさに最も大切な「簡潔さ」、この視点を持ち精査することで、魅力的で読みやすい文章に近づけられます。
首尾一貫しているか確認する
最後は記事全体がテーマに矛盾していないかを確認します。タイトル、サマリ、本文、まとめ内容の一貫性、起承転結は正しく構成されているかを見ます。このプロセスを妥協なく突き詰めることで更に読みやすい文章となります。
読みやすい文章を作るのに、言葉のセンスはさほど重要ではありません。最後のツメの作業である「読み返し」で、読み手の立場に立ったわかり易い表現に変えられるかがキモです。是非参考にしてみてください。
<ライタープロフィール>
担当ライター:俵谷龍佑
WordPressサイト制作/Web集客の専門家。大手広告代理店にて、百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのコンテンツライターとして活動中。執筆テーマは、集客やマーケティングなどビジネス関連、グルメや音楽関連。
公式ブログ/おれじなる
公式フェイスブック
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
[お子様文具] ジップパックちゅうしゃき シャープペン 指定不可 定価: 卸値:90円 |
|
定価: 卸値:16円 |
|
<アウトレット売切廃盤> [ケース入り筆記具] レザースタイルメタルペン ボールド 定価: 卸値:425円 |
★関連エントリー:
- 社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?/飯田橋事務所ニュース
- 外国人雇用、社会保険に加入させてますか/飯田橋事務所ニュース
- ホームページの申し込み数を最大化する「EFO」とは?
- 健康経営とは?メリットや導入ポイントを調べてみた
- 社員のSNS対策は必要?損害賠償を請求できる?/飯田橋事務所ニュース
- eメールで集客!今さら聞けないメールマーケティング
- 外国人雇用状況の届出を忘れずに/飯田橋事務所ニュース
カテゴリ:<専門家の解説> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
検索メニュー
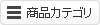


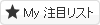
![ノベルティ:[お子様文具] ジップパックちゅうしゃき シャープペン](/img/item/Thumbnail19410Y09.jpg)



![ノベルティ:<アウトレット売切廃盤> [ケース入り筆記具] レザースタイルメタルペン ボールド](/img/item/ThumbnailTS-1103-009.jpg)