販促レポート
2019/05/24 専門家の解説
社員のSNS対策は必要?損害賠償を請求できる?/飯田橋事務所ニュース
従業員の不用意なSNS投稿が炎上し、企業が大きな損害を受けるケースが相次いています。従業員への損害賠償請求できるのでしょうか?本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。社員のSNS対策についての考察です。
社員のSNS対策は必要?損害賠償を請求できる?

従業員による不用意なSNS投稿が炎上し、企業が大きな損害を受けるケースが相次いています。信用失墜による顧客離れ、謝罪広告の掲載、休業、廃業に追い込まれるケースもあり、数千万、数億円単位の損害に膨れ上がることも珍しくありません。
大手外食チェーンのアルバイト店員が不衛生な悪ふざけ動画を投稿した事件では株価が暴落し、数十億円の損失とも報道されています。
会社は従業員にこれらの損害賠償を請求することはできるのでしょうか。
原則、一部しか認められない
結論から言うと、損害すべてを賠償してもらうことは難しでしょう。
損害賠償を請求したとしても一部しか認められない可能性が高いのです。なぜなら使用者は、労働者が働くことによって利益を得ているため、そこから生じるリスクも負担すべきと考えられているからです。
どれくらい損害賠償を減額するかは、労働者の過失の程度、地位、職責、労働条件、そして使用者の予防策、保険などの損失分散策などから判断されます。
まれに満額が認められたものも
まれに満額が認められたものもありますが、それは従業員が故意に会社に損害を与えた場合、具体的には会社のお金を横領した場合などよほど悪質なケースに限られています。
故意ではなく過失によて損害を与えた場合は、損害倍書請求は一部しか認められません。SNSの場合、悪ふざけがエスカレードしたものや、投稿すべきではないものをうっかり投稿してしまったというケースが多いため「過失」と判断され、一部しか認められない可能性が高いでしょう。
一部とはどれくらい?
「一部」の程度はケースバイケースですが、一例をご紹介しましょう。
過去に、そば屋の従業員が不衛生な悪ふざけをSNSに投稿して騒ぎになり、店が営業停止に追い込まれるという事件がありました。店はその後破産宣告を受けています。
店側は投稿に関わった授業員4人に対して1385万円の損害賠償請求をしましたが、その結果得られたのは合計200万程度の和解金です。
事前の防止策が重要
このように多大な被害を受けてもごく一部しか損害賠償が認められないことを考えると、事後の対処よりも事前の防止策に力を入れるべきことがおわかりいただけるでしょう。
事例を交えたわかりやすいルールを作って配布・掲示する、朝礼や研修で繰り返し教育するといった地道な防止策が何より重要なのです。
デジタルマネーによる給与の支払い解禁へ/労務ひとこと

政府がデジタルマネーによる給与の支払い解禁に向けて検討を進めています。
現在、給与の支払いは現金または銀行口座への振込みに限定されていますが、この規制を緩和して、銀行口座を通さずにICカードやスマートフォンの決済アプリなどに送金できるようにするというものです。
背景には、デジタル決済の普及によりキャッシュレス化を推進したいという狙いや、外国人労働者の受け入れ拡大があります。日本での保有資産等が少ない外国人は銀行口座の開設が難しく、銀行振込が当たり前となった昨今、給与支払いのために毎月多額の現金を用意しなければならないのは企業にとっても大きな負担です。
また、キャッシュレス化が進めば、レジに多額の現金を入れておく必要がなくなり、犯罪の防止につながるという意見もあります。
一方で、デジタルマネーの事業者が破綻した場合の労働者保護をどうすべきかなど課題もあります。報道では、2019年にもデジタルマネーによる給与支払いを解禁すると言われており、今年大きな動きがありそうです。
<ライタープロフィール>

従業員による不用意なSNS投稿が炎上し、企業が大きな損害を受けるケースが相次いています。信用失墜による顧客離れ、謝罪広告の掲載、休業、廃業に追い込まれるケースもあり、数千万、数億円単位の損害に膨れ上がることも珍しくありません。
大手外食チェーンのアルバイト店員が不衛生な悪ふざけ動画を投稿した事件では株価が暴落し、数十億円の損失とも報道されています。
会社は従業員にこれらの損害賠償を請求することはできるのでしょうか。
原則、一部しか認められない
結論から言うと、損害すべてを賠償してもらうことは難しでしょう。
損害賠償を請求したとしても一部しか認められない可能性が高いのです。なぜなら使用者は、労働者が働くことによって利益を得ているため、そこから生じるリスクも負担すべきと考えられているからです。
どれくらい損害賠償を減額するかは、労働者の過失の程度、地位、職責、労働条件、そして使用者の予防策、保険などの損失分散策などから判断されます。
まれに満額が認められたものも
まれに満額が認められたものもありますが、それは従業員が故意に会社に損害を与えた場合、具体的には会社のお金を横領した場合などよほど悪質なケースに限られています。
故意ではなく過失によて損害を与えた場合は、損害倍書請求は一部しか認められません。SNSの場合、悪ふざけがエスカレードしたものや、投稿すべきではないものをうっかり投稿してしまったというケースが多いため「過失」と判断され、一部しか認められない可能性が高いでしょう。
一部とはどれくらい?
「一部」の程度はケースバイケースですが、一例をご紹介しましょう。
過去に、そば屋の従業員が不衛生な悪ふざけをSNSに投稿して騒ぎになり、店が営業停止に追い込まれるという事件がありました。店はその後破産宣告を受けています。
店側は投稿に関わった授業員4人に対して1385万円の損害賠償請求をしましたが、その結果得られたのは合計200万程度の和解金です。
事前の防止策が重要
このように多大な被害を受けてもごく一部しか損害賠償が認められないことを考えると、事後の対処よりも事前の防止策に力を入れるべきことがおわかりいただけるでしょう。
事例を交えたわかりやすいルールを作って配布・掲示する、朝礼や研修で繰り返し教育するといった地道な防止策が何より重要なのです。
デジタルマネーによる給与の支払い解禁へ/労務ひとこと

政府がデジタルマネーによる給与の支払い解禁に向けて検討を進めています。
現在、給与の支払いは現金または銀行口座への振込みに限定されていますが、この規制を緩和して、銀行口座を通さずにICカードやスマートフォンの決済アプリなどに送金できるようにするというものです。
背景には、デジタル決済の普及によりキャッシュレス化を推進したいという狙いや、外国人労働者の受け入れ拡大があります。日本での保有資産等が少ない外国人は銀行口座の開設が難しく、銀行振込が当たり前となった昨今、給与支払いのために毎月多額の現金を用意しなければならないのは企業にとっても大きな負担です。
また、キャッシュレス化が進めば、レジに多額の現金を入れておく必要がなくなり、犯罪の防止につながるという意見もあります。
一方で、デジタルマネーの事業者が破綻した場合の労働者保護をどうすべきかなど課題もあります。報道では、2019年にもデジタルマネーによる給与支払いを解禁すると言われており、今年大きな動きがありそうです。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
公式WEBサイト
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
定価: 卸値:198円 |
★関連エントリー:
- 社員のネット対策、SNS利用を禁止できる?/飯田橋事務所ニュース
- 外国人雇用、社会保険に加入させてますか/飯田橋事務所ニュース
- ホームページの申し込み数を最大化する「EFO」とは?
- 健康経営とは?メリットや導入ポイントを調べてみた
- 社員のSNS対策は必要?損害賠償を請求できる?/飯田橋事務所ニュース
- eメールで集客!今さら聞けないメールマーケティング
- 外国人雇用状況の届出を忘れずに/飯田橋事務所ニュース
カテゴリ:<専門家の解説> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
検索メニュー
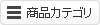


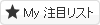
![ノベルティ:[扇風機] 3WAYポータブルファン](/img/item/ThumbnailMT-33243.jpg)






