販促レポート
2015/11/25 集客販促
集客術としての「値下げ」は、果たして正しいのだろうか?
客足が伸びないと、ついついやってしまう「値下げ」。一見、値下げはお客さんを呼び込むために有効な手段と思いがちですが、必ずしも正しいとは限りません。では、なぜ?値下げがいけないのか。今回はマーケティングの観点から「値下げ」について検証してみました。
お客さんが「値下げ」以上に求めているものを考えてみる

値段が安いことはメリットに感じられるかもしれません。しかし、お腹が空いたから飲食店に入る、旅行に行きたいから旅行代理店に行くといった単純な動機以上に、「自分の欲求を満たす」といった本来の目的を持つお客さんも多く存在することを知っておくべきでしょう。
値段も重要な要素の一つですが、自分の欲求をきちんと満たしてくれるサービスをお客さんは期待し求めているのです。「お気に入りだから」「思い出があるから」など、自分の欲求を満たす本来の目的を果たすことができれば、値段はさほど気にならないのです。
売上が上がらない不安を拭うために値下げをしてしまうと、サービス・商品に十分な投資をし続けられなくなり、お客さんのニーズを満たせないサービス・商品になってしまう可能性がありむしろ逆効果になるかもしれません。
ラーメン店を事例に挙げましょう。このラーメン店は650円で醤油ラーメンを販売していました。具だくさんでスープが並々いっぱいで提供されるラーメンは、一部のお客さんから高く支持されていました。もっと、多くのお客さんを呼び込もうと考え、」思い切って値段を500円にしました。この150円の分は、ラーメンの具材を減らす、スープの量を少なくすることで帳尻を合わせました。
この結果、どうなったかは言うまでもありません。
何度も訪れていた特定のファンは離れてしまい、「ただお腹が空いた人」が立ち寄るだけのお店になってしまいました。
値段を下げれば、一時的に人気店になるかもしれません。しかし品質が低下したサービスでは、今まで愛好してくれていたお客さんの足は遠のく可能性が高くなります。過去記事の「あなたの商品サービスを本当に必要としてるお客さんは誰ですか?」にも書いた通り、中小規模のお店・企業にとって、熱烈に支持してくれるファンの存在は非常に重要です。ファンが離れてしまえば、良い口コミもされなくなって売上は伸び悩みます。
過去記事:あなたの商品サービスを本当に必要としてるお客さんは誰ですか?
過度な値下げは、自分の首を絞めることになる

前章で、値下げを行えばファンが離れるという話をしました。しかし、それだけではありません。値下げをすることでクレームが増える可能性が高まります。理由は、「低価格という部分にしか魅力を感じていないお客さんが増えるため」です。安い価格には安っぽい印象しか感じることができず、悪いことを粗探ししようという心理が働きがちになるようです。これについては、『お客様がずっと通いたくなる「極上の接客」』(向井邦雄/同文舘出版)で詳しく書かれています。
結果的に値下げする以前よりも仕事が増えてしまい、そのわりには利益が少ないという悪循環に陥ることになるのです。閉店した店舗やクローズに追い込まれたサービスのほとんどは、このようなケースを経験しているのではないでしょうか。企業経営やサービス運営としては、この負のスパイラルは何としても避けなければならないポイントです。
値上げをしても安く見えるコツ、効果的な値下げ演出

とはいっても、勇気を持って値段を上げるのはなかなか難しいことです。しかし、ユーザーに高いと思わせることなく値上げをする方法があります。それをいくつか簡単に紹介したいと思います。
<端数で値付けをする>
例えば、20,000円の商品を19,800円と表記する方法です。これを「端数価格」と呼びます。小売業では幅広く用いられている手法です。端数にすることでギリギリまで下げているという印象を与えることができます。
<価格帯を複数用意する>
お寿司屋さんのメニューが分かりやすい例でしょう。特上、上、並のように価格帯を複数用意します。この手法の最大の目的は、多くのお客さんを集めるためではなく、中間の価格帯にお客さんを誘導させることです。人間はちょうど良いものを選ぶという習性があります。これを「松竹梅の法則」といいます。
たとえば、ディナーのコースで、3,500円、5,000円、9,000円という価格帯があるとします。お客さんの心理としては、「さすがに9,000円は高い。3,500円も安くて良いけれど、せっかくきたから5,000円にしとこう」となるわけです。たとえ値上げをしても、複数の価格帯が用意されていれば、高いと感じることはありません。
<お得感を演出する>
例えば、3,000円の商品を5,000円に値上げするとします。その際に一手間加えて6,000→5,000円と表記します。これだけで不思議とお得感を演出することができます。しかし、あまりにかけ離れた金額を書いてしまうと「二重価格表示」という違法行為になるので、やりすぎには注意しましょう。
ファンを満足させるために安易な値下げはやらない
本当にあなたを必要としているお客さんは、「お気に入りだから」「思い出があるから」など、幸福な体験に価値を感じているはずです。そして、そのようなお客さんは、値下げをしなくとも適正な対価を快く支払ってくれているはずです。サービス・商品に満足をしてるのだから当たり前の話ですね。
また、サービス・商品の品質維持や品質向上には、創意工夫と応分の手間コストがかかります。安易な値下げをすることで、この部分に予算や時間が行き渡らないようでは、サービス・商品の魅力を維持できなくなるのは言うまでもありません。
値下げをしないことによる適切な儲けがあれば、サービス・商品を磨くことに予算を割くことができます。結果としてお客さんの満足度を高め、さらなるファンの獲得に繋がる好循環に舵をきることができるかもしれません。ファンを満足させるために、安易な値下げはやってはならないのです。
<ライタープロフィール>

値段が安いことはメリットに感じられるかもしれません。しかし、お腹が空いたから飲食店に入る、旅行に行きたいから旅行代理店に行くといった単純な動機以上に、「自分の欲求を満たす」といった本来の目的を持つお客さんも多く存在することを知っておくべきでしょう。
値段も重要な要素の一つですが、自分の欲求をきちんと満たしてくれるサービスをお客さんは期待し求めているのです。「お気に入りだから」「思い出があるから」など、自分の欲求を満たす本来の目的を果たすことができれば、値段はさほど気にならないのです。
売上が上がらない不安を拭うために値下げをしてしまうと、サービス・商品に十分な投資をし続けられなくなり、お客さんのニーズを満たせないサービス・商品になってしまう可能性がありむしろ逆効果になるかもしれません。
ラーメン店を事例に挙げましょう。このラーメン店は650円で醤油ラーメンを販売していました。具だくさんでスープが並々いっぱいで提供されるラーメンは、一部のお客さんから高く支持されていました。もっと、多くのお客さんを呼び込もうと考え、」思い切って値段を500円にしました。この150円の分は、ラーメンの具材を減らす、スープの量を少なくすることで帳尻を合わせました。
この結果、どうなったかは言うまでもありません。
何度も訪れていた特定のファンは離れてしまい、「ただお腹が空いた人」が立ち寄るだけのお店になってしまいました。
値段を下げれば、一時的に人気店になるかもしれません。しかし品質が低下したサービスでは、今まで愛好してくれていたお客さんの足は遠のく可能性が高くなります。過去記事の「あなたの商品サービスを本当に必要としてるお客さんは誰ですか?」にも書いた通り、中小規模のお店・企業にとって、熱烈に支持してくれるファンの存在は非常に重要です。ファンが離れてしまえば、良い口コミもされなくなって売上は伸び悩みます。
過去記事:あなたの商品サービスを本当に必要としてるお客さんは誰ですか?
過度な値下げは、自分の首を絞めることになる

前章で、値下げを行えばファンが離れるという話をしました。しかし、それだけではありません。値下げをすることでクレームが増える可能性が高まります。理由は、「低価格という部分にしか魅力を感じていないお客さんが増えるため」です。安い価格には安っぽい印象しか感じることができず、悪いことを粗探ししようという心理が働きがちになるようです。これについては、『お客様がずっと通いたくなる「極上の接客」』(向井邦雄/同文舘出版)で詳しく書かれています。
そもそも、クーポンなどの割引サービスを利用する客や、キャッシュバックを目当てに来る客は、本来の価値に見合った定価を定価だとは思っていません。
割引後の価格が定価だと思って来店してくるのです。
その店や商品に元の定価分の価値を感じていない人ですから、満足もしない、不満に感じる、クレームを言うという流れになっていきます。
参照:お客様がずっと通いたくなる「極上の接客」(向井邦雄/同文舘出版)
結果的に値下げする以前よりも仕事が増えてしまい、そのわりには利益が少ないという悪循環に陥ることになるのです。閉店した店舗やクローズに追い込まれたサービスのほとんどは、このようなケースを経験しているのではないでしょうか。企業経営やサービス運営としては、この負のスパイラルは何としても避けなければならないポイントです。
値上げをしても安く見えるコツ、効果的な値下げ演出

とはいっても、勇気を持って値段を上げるのはなかなか難しいことです。しかし、ユーザーに高いと思わせることなく値上げをする方法があります。それをいくつか簡単に紹介したいと思います。
<端数で値付けをする>
例えば、20,000円の商品を19,800円と表記する方法です。これを「端数価格」と呼びます。小売業では幅広く用いられている手法です。端数にすることでギリギリまで下げているという印象を与えることができます。
<価格帯を複数用意する>
お寿司屋さんのメニューが分かりやすい例でしょう。特上、上、並のように価格帯を複数用意します。この手法の最大の目的は、多くのお客さんを集めるためではなく、中間の価格帯にお客さんを誘導させることです。人間はちょうど良いものを選ぶという習性があります。これを「松竹梅の法則」といいます。
たとえば、ディナーのコースで、3,500円、5,000円、9,000円という価格帯があるとします。お客さんの心理としては、「さすがに9,000円は高い。3,500円も安くて良いけれど、せっかくきたから5,000円にしとこう」となるわけです。たとえ値上げをしても、複数の価格帯が用意されていれば、高いと感じることはありません。
<お得感を演出する>
例えば、3,000円の商品を5,000円に値上げするとします。その際に一手間加えて6,000→5,000円と表記します。これだけで不思議とお得感を演出することができます。しかし、あまりにかけ離れた金額を書いてしまうと「二重価格表示」という違法行為になるので、やりすぎには注意しましょう。
ファンを満足させるために安易な値下げはやらない
本当にあなたを必要としているお客さんは、「お気に入りだから」「思い出があるから」など、幸福な体験に価値を感じているはずです。そして、そのようなお客さんは、値下げをしなくとも適正な対価を快く支払ってくれているはずです。サービス・商品に満足をしてるのだから当たり前の話ですね。
また、サービス・商品の品質維持や品質向上には、創意工夫と応分の手間コストがかかります。安易な値下げをすることで、この部分に予算や時間が行き渡らないようでは、サービス・商品の魅力を維持できなくなるのは言うまでもありません。
値下げをしないことによる適切な儲けがあれば、サービス・商品を磨くことに予算を割くことができます。結果としてお客さんの満足度を高め、さらなるファンの獲得に繋がる好循環に舵をきることができるかもしれません。ファンを満足させるために、安易な値下げはやってはならないのです。
<ライタープロフィール>
担当ライター:ryusuke
大手広告代理店にて、顧客である百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのWebライターとして活動中。執筆テーマは、グルメ関連やビジネス関連など、その他様々な分野のコラムや解説を得意とします。
公式ブログ
公式フェイスブック
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
定価: 卸値:46円 |
|
定価: 卸値:34円 |
|
定価: 卸値:613円 |
★関連エントリー:
- 定番のエリアマーケティング!反応率の高いポスティングの活用法
- 記憶に残る商品ネーミング、ロングセラーから学ぶ!
- 少ないアクセスでも注文殺到!そんなWEBサイトの共通点を探る
- やらなきゃ大損!グーグル最新SEO攻略「YMYL」とは
- 売上を最大化する魔法のテク!セールスライティング|実践編
- 売上を最大化する魔法のテク!セールスライティング|基本編
- ホームページ運用の重要指標「コンバージョン」とは?
カテゴリ:<集客販促> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
検索メニュー
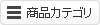


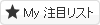
![ノベルティ:[ビューティケア] 楽コロ 4色ボールペン](/img/item/Thumbnail437Y04.jpg)

![ノベルティ:[ビューティケア] 楽コロ 4色ボールペンのレビュー](/img/ic_document.gif)










