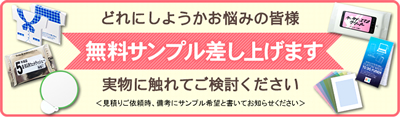販促レポート
2017/04/04 仕事術ハック
同じ失敗を繰り返さない、うっかりミスを防ぐ方法とは
気をつけているのに「ミスをしてしまう」「同じ失敗をしてしまう」という悩みを抱えている方もいるでしょう。そのミスをなくすためには、まずミスの種類を知り、それに見合う対処が必要です。今回は、「うっかり」を防ぐための対処法を紹介します。
仕事での「つい」や「うっかり」は命取りになるかもしれない

会社や店舗などで、頼まれていた仕事を「するのを忘れてしまった」や、メモをしていなかったから「内容を忘れてしまった」という「ついうっかり」の経験はありませんか?
それによってお客さんに迷惑を掛けてしまったり、社内で信頼を失ってしまったりと、仕事上での「つい」や「うっかり」は命取りになりかねません。どんなに記憶力のいい人でも、立て続けに電話を取り、社内の人とも会話をしている状態では、全てを正確に覚えることは難しいと言われています。
少し古いデータですが、社会人を対象に実施した「職場で上司に怒られると焦った失敗を教えてください」という、ニュースサイトマイナビのアンケート結果をご紹介いたします。
これによると、「頼まれていた仕事をすっかり忘れていたとき」が1位で、24.8%。つまり4人に1人が、「つい」や「うっかり」による失敗経験を一番の教訓としていることになります。
このことからも分かるよう、「つい」や「うっかり」は誰にでもあり得る一方で、誰もが「気を付けるべき」と認識しているようです。では、うっかりミスを防ぐためには、どのような具体的な心がけが必要なのでしょうか。
忘れることは、人間の宿命

まずは、ミスの種類を知ることから始めましょう。
何かを忘れてしまったというのは、「メモリーミス」と言われます。それ以外に、見落としによるミスを「アテンションミス」、ちゃんと伝わらなかった、聞いていなかったなどは「コミュニケーションミス」、判断を誤ることを「ジャッジメントミス」と言います。
今回は、中でも多くの人に経験があるであろう「メモリーミス」についてご紹介します。
ワーキングメモリと呼ばれる短期記憶を司る、脳のメモ機能がメモリーミスの原因と言われています。ワーキングメモリの容量はとても小さいため、立て続けにいろいろなことが起こると、容量が足りず忘れてしまう構造になっているそうです。
ところで皆さんは、「エビングハウスの忘却曲線」というものをご存知でしょうか。ドイツの学者であるエビングハウスが発見した、人は何かを学んだ時、
という記憶の忘却曲線と呼ばれるものを言います。これは人間である以上は、避けては通れない忘却システムで、これにより人は嫌なことがあっても、「精神状態を正常に保つ」ことができるのだそうです。
しかし、、、仕事では「忘れてはいけないこと」がたくさんある、というのが現実です。
メモを習慣化し、うっかりミスを防ぐ

残念ながら、脳内のワーキングメモリという機能は、トレーニングで鍛えられないという説があります。では、どのような手を打てば、メモリーミスを防ぐことができるのでしょうか。
答えはとてもシンプル。自分の記憶を過信するのではなく、「必ずメモを取ることを習慣化」することです。また、メモを取る際は、下記の三つに注意することで、さらに効率よく「ついうっかり」を防ぐことができます。
すぐにメモをとれる環境を用意しておく
常にメモをとれる環境を、整えておくことが大切です。決まったメモ帳を常に持ち歩くか、スマートフォンとパソコンで、同期できるメモ帳を利用するのでも構いません。とにかく、常にメモをとれる環境を作り、記憶に頼らず一言でもメモを残すようにしましょう。
同じ場所を確認するようにする
メモを取る場所を分散させてしまうと、そのメモが見えなければ何の意味もありません。メモを取るもの・場所はできるだけ統一し、デスクに座ったらまずそこを見る、とルーティン化させましょう。パソコンでもデスクトップですぐに確認できる場所に保存します。
翌日以降使わない情報は退社時に破棄する
メモの情報が多くなりすぎると、次のミスにも繋がりかねません。電話の取り次ぎ時のメモや、明日以降使うことのないメモは、捨てるか、思い切って削除しておきましょう。明日以降も使う情報は翌日の朝、デスクに座った時に必ず最初に確認するようにします。
いかがでしたでしょうか。
記憶力に自信がある人こそ、自分の記憶力に頼りがちになります。人間に共通する脳の仕組みを理解し、こまめにメモを取ることを習慣化していけば、ミスを減らすことができます。ぜひ、実践してみてください。
なお本稿は、「仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方」著者:宇都出雅巳、出版:株式会社クロスメディア・パブリッシングを参照し執筆いたしました。ご興味のある方は、実際に手に取って本書をお読みください。とても参考になります。
参照:仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方|アマゾン
<ライタープロフィール>

会社や店舗などで、頼まれていた仕事を「するのを忘れてしまった」や、メモをしていなかったから「内容を忘れてしまった」という「ついうっかり」の経験はありませんか?
それによってお客さんに迷惑を掛けてしまったり、社内で信頼を失ってしまったりと、仕事上での「つい」や「うっかり」は命取りになりかねません。どんなに記憶力のいい人でも、立て続けに電話を取り、社内の人とも会話をしている状態では、全てを正確に覚えることは難しいと言われています。
少し古いデータですが、社会人を対象に実施した「職場で上司に怒られると焦った失敗を教えてください」という、ニュースサイトマイナビのアンケート結果をご紹介いたします。
引用元:【男性編】職場で上司に怒られると焦った失敗ランキング
- 1位 頼まれていた仕事をすっかり忘れていたとき 24.8%
- 2位 電話の取り次ぎメモを書き残すのを忘れた 16.8%
- 3位 会議中眠ってしまい手に持っていた資料やペンを落としてしまった 15.9%
- 4位 上司あての電話をかけてきた相手の名前を聞き忘れたor聞き間違えた 14.9%
- 5位 会議の資料や企画書に誤字があったとき 11.2%
これによると、「頼まれていた仕事をすっかり忘れていたとき」が1位で、24.8%。つまり4人に1人が、「つい」や「うっかり」による失敗経験を一番の教訓としていることになります。
このことからも分かるよう、「つい」や「うっかり」は誰にでもあり得る一方で、誰もが「気を付けるべき」と認識しているようです。では、うっかりミスを防ぐためには、どのような具体的な心がけが必要なのでしょうか。
忘れることは、人間の宿命

まずは、ミスの種類を知ることから始めましょう。
何かを忘れてしまったというのは、「メモリーミス」と言われます。それ以外に、見落としによるミスを「アテンションミス」、ちゃんと伝わらなかった、聞いていなかったなどは「コミュニケーションミス」、判断を誤ることを「ジャッジメントミス」と言います。
今回は、中でも多くの人に経験があるであろう「メモリーミス」についてご紹介します。
ワーキングメモリと呼ばれる短期記憶を司る、脳のメモ機能がメモリーミスの原因と言われています。ワーキングメモリの容量はとても小さいため、立て続けにいろいろなことが起こると、容量が足りず忘れてしまう構造になっているそうです。
ところで皆さんは、「エビングハウスの忘却曲線」というものをご存知でしょうか。ドイツの学者であるエビングハウスが発見した、人は何かを学んだ時、
- 20分後には、42%忘れる
- 1時間後には、56%忘れる
- 1日後には、74%忘れる
- 7日後には、77%忘れる
- 31日後には、79%忘れる
という記憶の忘却曲線と呼ばれるものを言います。これは人間である以上は、避けては通れない忘却システムで、これにより人は嫌なことがあっても、「精神状態を正常に保つ」ことができるのだそうです。
しかし、、、仕事では「忘れてはいけないこと」がたくさんある、というのが現実です。
メモを習慣化し、うっかりミスを防ぐ

残念ながら、脳内のワーキングメモリという機能は、トレーニングで鍛えられないという説があります。では、どのような手を打てば、メモリーミスを防ぐことができるのでしょうか。
答えはとてもシンプル。自分の記憶を過信するのではなく、「必ずメモを取ることを習慣化」することです。また、メモを取る際は、下記の三つに注意することで、さらに効率よく「ついうっかり」を防ぐことができます。
すぐにメモをとれる環境を用意しておく
常にメモをとれる環境を、整えておくことが大切です。決まったメモ帳を常に持ち歩くか、スマートフォンとパソコンで、同期できるメモ帳を利用するのでも構いません。とにかく、常にメモをとれる環境を作り、記憶に頼らず一言でもメモを残すようにしましょう。
同じ場所を確認するようにする
メモを取る場所を分散させてしまうと、そのメモが見えなければ何の意味もありません。メモを取るもの・場所はできるだけ統一し、デスクに座ったらまずそこを見る、とルーティン化させましょう。パソコンでもデスクトップですぐに確認できる場所に保存します。
翌日以降使わない情報は退社時に破棄する
メモの情報が多くなりすぎると、次のミスにも繋がりかねません。電話の取り次ぎ時のメモや、明日以降使うことのないメモは、捨てるか、思い切って削除しておきましょう。明日以降も使う情報は翌日の朝、デスクに座った時に必ず最初に確認するようにします。
いかがでしたでしょうか。
記憶力に自信がある人こそ、自分の記憶力に頼りがちになります。人間に共通する脳の仕組みを理解し、こまめにメモを取ることを習慣化していけば、ミスを減らすことができます。ぜひ、実践してみてください。
なお本稿は、「仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方」著者:宇都出雅巳、出版:株式会社クロスメディア・パブリッシングを参照し執筆いたしました。ご興味のある方は、実際に手に取って本書をお読みください。とても参考になります。
参照:仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方|アマゾン
<ライタープロフィール>
担当ライター:h.kuga
企業ブログアドバイザー・フリーライター・ブロガー。早稲田大学卒業後、教育系出版社にて私立大学等への広告営業を担当、新規事業企画にも携わる。現在は、日々、企業ブログの可能性とアクセス数アップのための施策について研究を深めている。特に、経済系・ライフハック系・商品紹介の記事を得意とする。
公式サイト
公式フェイスブック
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
定価: 卸値:135円 |
|
[粗品(文具)] 熨斗(のし)ふせん(印刷0円代) ありがとう 定価: 卸値:170円 |
|
定価: 卸値:300円 |
★関連エントリー:
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【明大前・桜上水エリア編】
- もう誤解を生まない!正しく伝わるオンラインコミュニケーション
- 3分でわかる採用ブランディング!メリットや方法を考察
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【恵比寿エリア編】
- 教え上手になろう!伝わる教え方の重要ポイント5つ
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(実践編)
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(基本編)
カテゴリ:<仕事術ハック> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
束入れ | 記念掛時計 | フィラ | シュレッダー | ロゼミュール | 保冷温バッグ | ショルダーバッグ | マグカップ
検索メニュー
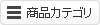


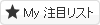




![ノベルティ:[粗品(文具)] 熨斗(のし)ふせん(印刷0円代)](/img/item/Thumbnailh-104800.jpg)