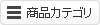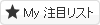販促レポート
2019/03/27 仕事術ハック
3分でわかる採用ブランディング!メリットや方法を考察
求人を出しても応募がない。そんな悩みなら「採用ブランディング」を検討してみましょう。採用ブランディングは、従来より低コストで自社にマッチした人材を集められるそう。果たしてどんな点が優れているのでしょう。
なぜ、採用ブランディングが必要か?

まず、採用ブランディングとは何か?改めて定義をおさらいしたいと思います。採用ブランディングとは、
現在、多くの企業は人材不足に頭を悩ませています。帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査」では、2018年に人手不足が原因で倒産した件数は153件で、前年と比べると44.3%も増加しています。
人手不足に対する企業の動向調査|帝国データバンク
また、日本政策金融公庫が行った「小企業の雇用に関する調査結果」でも、従業員が不足していると回答した割合は37.7%で、9年連続でポイントが上昇しています。
小企業の雇用に関する調査結果|日本政策金融
これほどまでに人手不足が進んでいる背景には、少子高齢化による労働人口の減少が大きく関わっているようです。
このような状況下では、有効求人倍率は上がり、採用コストも高くなります。大手企業であれば採用競争で勝ち残れますが、多額のコストを投下できない中小ベンチャー企業は採用活動への工夫が求められます。
そこで重要になってくるのが「採用ブランディング」という考え方です。
採用ブランディングと聞くと難しく感じてしまいますが、要は、【誰に(求める人物像)】、【何を(自社の強みやビジョン)】、【どのようにして(発信方法)】伝えるかを決めることです。ここがきちんと設計できれば、求職者に自社の強みやビジョンをアピールすることができ、効率的な採用を行うことができるようになるでしょう。
採用ブランディングを行うメリット
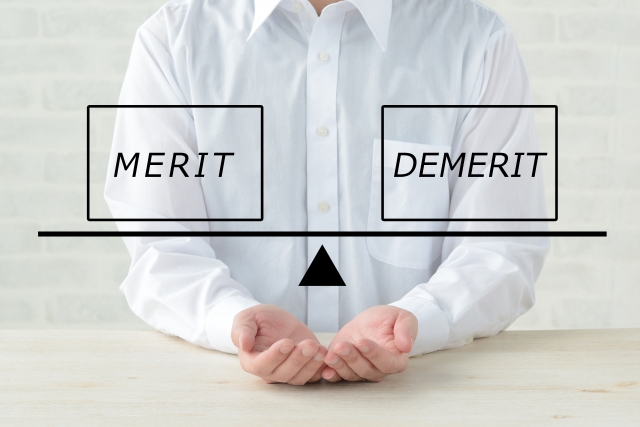
では、採用ブランディングを積極的に取り組むと、どのようなメリットがあるのでしょうか?以下の3つを考察してみました。
条件に見合った応募者を増やせる
闇雲に応募者を増やしても、選考の手間や採用コストがかさむだけで、かえって逆効果です。正しく採用ブランディングが行われていれば、求めるターゲットに適切な情報を届けることができるため、より条件に見合った応募者を増やすことができます。
離職率低下につながる
採用ブランディングでは企業・求職者の相互理解を重視するため、ミスマッチが起きにくくなります。よくありがちな「実際に働いてみたら、思っていたイメージと違った」というケースが少なくなるため、長く働いてくれる従業員が多くなります。
採用コストを削減できる
大量のエントリーから条件にマッチする人材を探すのではなく、【誰に(求める人物像)】、【何を(自社の強みやビジョン)】、【どのようにして(発信方法)】伝えるかという部分を明確する採用活動のため、採用コストを最小限に抑えられます。
採用ブランディングを行う方法

採用ブランディングの活動の肝は、【誰に】【何を】【どのようにして】伝えるかということは、冒頭でもお伝えしましたが具体的にどのようなことを行うのでしょう?
入社してもらいたい人物像を明確にする
採用ブランディングで最も大切なポイントはここです。ターゲットを絞る時は、職種やスキルだけでなく、「指示に従って一人で黙々と作業できる人」のように求める人物のキャラクターを言語化することが重要です。想起しにくい場合は、すでに社内にいる社員を参考に作り上げてましょう。
企業のPRポイントを再定義する
ターゲットが明確になったら、次は企業のPRポイントを再定義します。「ビジョン」「事業内容」「企業風土・人」の3つで考えましょう。例えば、「自由闊達な雰囲気です」のように抽象的だと、どこかで聞いた事あるありきたりなメッセージになってしまうので、どのように自由なのかを具体的にします。
ターゲットに適した採用キャッチコピーを考える
PRポイントが決まったら、自社の採用キャッチコピーを作ります。求める人物像の条件の中で最も優先度の高いものを基準に作りましょう。例えば、柔軟思考の人が欲しい際は、「課題を面白がろう」のコピーのように、明快な一言に要約し、求職者の記憶に残すことができます。
求職者との接点を増やす
有名な大手就職支援サイトやハローワークに求人を掲載するだけでなく、自社ホームページ、SNS、ブログ、説明会、インターンシップなど、主体的に情報を発信することも忘れずに行いましょう。求職者が採用情報にアクセスしやすいよう、さまざまな接点機会を用意するのが重要です。
発信する内容に統一感を持たせる
最後に、これまでに挙げた1~4のポイントに矛盾がないかを確認します。今は、SNSで手軽に企業の評判や噂が手に入る時代、求職者は企業のあらゆる側面を見て「入社すべきかどうか」評価しています。社内で連携し、従業員の振る舞いからSNSの発言まで徹底してブランディングしましょう。
採用ブランディングを上手に取り入れることができれば、優秀な人材確保ができるだけでなく、離職率の低下や採用コスト削減にもつなげることができます。採用難の今だからこそ、積極的に採用ブランディングを行い、「ここで働きたい」と思ってもらえるような企業ブランドを醸成していきましょう。

まず、採用ブランディングとは何か?改めて定義をおさらいしたいと思います。採用ブランディングとは、
求職者に『あの企業に入社したい』と思ってもらえるよう、自社ならではの強みや企業理念やビジョンをPRし、採用面で良いブランドを構築する活動全般のことを指します。
現在、多くの企業は人材不足に頭を悩ませています。帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査」では、2018年に人手不足が原因で倒産した件数は153件で、前年と比べると44.3%も増加しています。
人手不足に対する企業の動向調査|帝国データバンク
また、日本政策金融公庫が行った「小企業の雇用に関する調査結果」でも、従業員が不足していると回答した割合は37.7%で、9年連続でポイントが上昇しています。
小企業の雇用に関する調査結果|日本政策金融
これほどまでに人手不足が進んでいる背景には、少子高齢化による労働人口の減少が大きく関わっているようです。
このような状況下では、有効求人倍率は上がり、採用コストも高くなります。大手企業であれば採用競争で勝ち残れますが、多額のコストを投下できない中小ベンチャー企業は採用活動への工夫が求められます。
そこで重要になってくるのが「採用ブランディング」という考え方です。
採用ブランディングと聞くと難しく感じてしまいますが、要は、【誰に(求める人物像)】、【何を(自社の強みやビジョン)】、【どのようにして(発信方法)】伝えるかを決めることです。ここがきちんと設計できれば、求職者に自社の強みやビジョンをアピールすることができ、効率的な採用を行うことができるようになるでしょう。
採用ブランディングを行うメリット
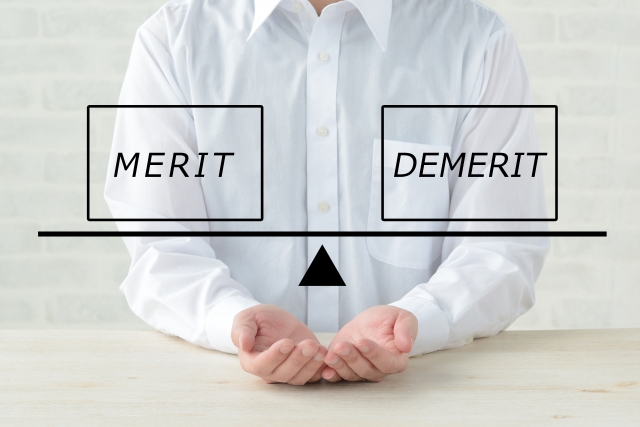
では、採用ブランディングを積極的に取り組むと、どのようなメリットがあるのでしょうか?以下の3つを考察してみました。
条件に見合った応募者を増やせる
闇雲に応募者を増やしても、選考の手間や採用コストがかさむだけで、かえって逆効果です。正しく採用ブランディングが行われていれば、求めるターゲットに適切な情報を届けることができるため、より条件に見合った応募者を増やすことができます。
離職率低下につながる
採用ブランディングでは企業・求職者の相互理解を重視するため、ミスマッチが起きにくくなります。よくありがちな「実際に働いてみたら、思っていたイメージと違った」というケースが少なくなるため、長く働いてくれる従業員が多くなります。
採用コストを削減できる
大量のエントリーから条件にマッチする人材を探すのではなく、【誰に(求める人物像)】、【何を(自社の強みやビジョン)】、【どのようにして(発信方法)】伝えるかという部分を明確する採用活動のため、採用コストを最小限に抑えられます。
採用ブランディングを行う方法

採用ブランディングの活動の肝は、【誰に】【何を】【どのようにして】伝えるかということは、冒頭でもお伝えしましたが具体的にどのようなことを行うのでしょう?
入社してもらいたい人物像を明確にする
採用ブランディングで最も大切なポイントはここです。ターゲットを絞る時は、職種やスキルだけでなく、「指示に従って一人で黙々と作業できる人」のように求める人物のキャラクターを言語化することが重要です。想起しにくい場合は、すでに社内にいる社員を参考に作り上げてましょう。
企業のPRポイントを再定義する
ターゲットが明確になったら、次は企業のPRポイントを再定義します。「ビジョン」「事業内容」「企業風土・人」の3つで考えましょう。例えば、「自由闊達な雰囲気です」のように抽象的だと、どこかで聞いた事あるありきたりなメッセージになってしまうので、どのように自由なのかを具体的にします。
ターゲットに適した採用キャッチコピーを考える
PRポイントが決まったら、自社の採用キャッチコピーを作ります。求める人物像の条件の中で最も優先度の高いものを基準に作りましょう。例えば、柔軟思考の人が欲しい際は、「課題を面白がろう」のコピーのように、明快な一言に要約し、求職者の記憶に残すことができます。
求職者との接点を増やす
有名な大手就職支援サイトやハローワークに求人を掲載するだけでなく、自社ホームページ、SNS、ブログ、説明会、インターンシップなど、主体的に情報を発信することも忘れずに行いましょう。求職者が採用情報にアクセスしやすいよう、さまざまな接点機会を用意するのが重要です。
発信する内容に統一感を持たせる
最後に、これまでに挙げた1~4のポイントに矛盾がないかを確認します。今は、SNSで手軽に企業の評判や噂が手に入る時代、求職者は企業のあらゆる側面を見て「入社すべきかどうか」評価しています。社内で連携し、従業員の振る舞いからSNSの発言まで徹底してブランディングしましょう。
採用ブランディングを上手に取り入れることができれば、優秀な人材確保ができるだけでなく、離職率の低下や採用コスト削減にもつなげることができます。採用難の今だからこそ、積極的に採用ブランディングを行い、「ここで働きたい」と思ってもらえるような企業ブランドを醸成していきましょう。
担当ライター:俵谷龍佑
WordPressサイト制作/Web集客の専門家。大手広告代理店にて、百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのコンテンツライターとして活動中。執筆テーマは、集客やマーケティングなどビジネス関連、グルメや音楽関連。
公式ブログ
公式フェイスブック
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
定価: 卸値:200円 |
|
定価: 卸値:475円 |
|
定価: 卸値:665円 |
★関連エントリー:
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【明大前・桜上水エリア編】
- もう誤解を生まない!正しく伝わるオンラインコミュニケーション
- 3分でわかる採用ブランディング!メリットや方法を考察
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【恵比寿エリア編】
- 教え上手になろう!伝わる教え方の重要ポイント5つ
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(実践編)
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(基本編)
カテゴリ:<仕事術ハック> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
トラベル用品 | 温湿度計 | アルバム | スヌーピー | マチあり | デジタルクロック | スピーカー | 真空断熱マグ
検索メニュー