販促レポート
2017/03/22 仕事術ハック
マネて学ぶスキルアップ!「真似る技術」を習得する5つのポイント
誰しも駆け出しの頃は、先輩や上司、尊敬する人を真似てスキルを高めます。それはいかに有能な人でも同じで、最初から完璧な人はいないからです。真似ることは、一見、パクリと混同されがちですが違いは何なのでしょう。今回は、この「真似」について考察します。
似て非なる「真似る」と「パクる」の違い

真似るというと、他人のアイデアを「横取りする」というように、つい「パクリ」と同様にネガティブな印象を受けてしまいます。しかし、「真似る」行為と「パクる」行為では、大きく意味合いが異なります。筆者(@tawarayaryusuke)の個人的な解釈となりますが、以下にてそれぞれご紹介。
つまり「真似る」には模倣に加え、「自分の色を出す」という一手間が加わっていますが、パクリにはそれがありません。
また、実はこの「真似る」行為、はるか昔から重宝されてきており、有名な偉人や成功者の名言からも、その重要性を垣間見ることができます。
何か新しいスキルを身につける時、大きな仕事を成功させようとする時、まっさらな状態からスタートするようでは気が遠くなります。けれど、実は偉人らも最初から作り上げることはせず、既存のものを組み合わせて価値を生みだしたようです。
何も参考にせず、自分の頭の中の限られた知識や経験則に頼るだけでは、新しい発想は生まれませんし、いつか行き詰まってしまうでしょう。何事においても、真似をするということは非常に大切で合理的なことなのです。
真似るのが苦手な人によく見られる特徴

冒頭では、新しいスキルを身につける、新しいことを成し遂げるには、真似ることが大切であるということをお話ししました。ここで、改めて真似るのが苦手な人によく見られる特徴についてまとめてみました。当てはまる項目が多い方は要注意です。
真似ることを卑怯なことと思い込んでいる
真似ることが苦手な人は、総じて真似ることは卑怯なことと認識しています。真似ることは、効率的にスキルや知識を身につける手段の一つに過ぎません。問題なのは、そっくりそのまま真似をすることであって、最終的に真似をしたスキルや知識を自分なりに昇華すれば問題ないのです。
仕事を覚えるのに時間がかかる
有能な人の真似をせずに、とにかく自分流でやってみようと動く傾向にあります。自分のやりやすい方法で行った方が効率的と思い込んでいて、結果的に一つの仕事を習得するまでに人一倍時間がかかってしまうのです。
視野が狭い、自分なりのこだわりを持ちすぎている
真似ることを敬遠しているので、我流なままで一向に視野が広がりません。こだわりを持ちすぎて、アドバイスされても、「それは自分に向かないから」とすぐに断ってしまう傾向にあります。結果的に、どんどん自分流に傾いて視野狭窄になってしまうでしょう。
真似る技術を習得する5つのポイント

では、真似る技術を習得する上でどのようなポイントが大切になるのでしょうか?それは、以下の5つのポイントに集約されます。
常識にとらわれないようにする
真似るということは、つまり新しい価値観や考えを自分の中に取り込むということです。今持っている常識にとらわれると、なかなか新しい価値観や考えは取り込めません。まっさらな素直な気持ちで真似ることが大切です。
人の行動や考えを観察する眼を養う
真似る上で欠かせないのが真似るポイントを把握すること。把握するには、観察が欠かせません。真似をしたいと思う人のまばたき、呼吸、視線、クセなど細かい部分を徹底的に観察しましょう。観察眼を養うことで、自然と真似をした方が良いポイントを把握できるようになるでしょう。
行動量を増やす
真似する行為と関係がないように思えますが、実は非常に関連性が高いです。なぜなら、考えているだけでは真似る技術は上達しないからです。行動を重ねるからこそ、どんどん真似が上手くなるのです。真似るには、とにかく色んな方法を試して真似ができるように努力することが大切です。
様々なものや人を参考にする
一つのものや人よりも、いろんなものや人を「真似の対象」にしましょう。一つでも良いですが、複数のものや人を対象にした方がより多角的な視点、気付きを得られます。また、それぞれの良いところ悪いところも客観的に見ることができるでしょう。
真似だけでなく自分なりの色を加える
真似をすることができたら、自分なりの色を加えましょう。冒頭でも書いたように、ただ真似をするだけでは「模倣したもの」にとどまってしまいます。自分なりに昇華させて、初めて「真似る」ことができたといえるのです。
いかがでしたでしょうか。
たとえ有能な人であっても、最初は先輩や上司を徹底的に真似るところから始まり、そしてそこから得た知識や知恵を自分なりに咀嚼し、自分の血肉にしているのです。あなたも早速、身近にいる優秀な人を真似しできるビジネスマンを目指しましょう。ぜひ、参考にしてみてください。
<ライタープロフィール>

真似るというと、他人のアイデアを「横取りする」というように、つい「パクリ」と同様にネガティブな印象を受けてしまいます。しかし、「真似る」行為と「パクる」行為では、大きく意味合いが異なります。筆者(@tawarayaryusuke)の個人的な解釈となりますが、以下にてそれぞれご紹介。
- 真似る・・・オリジナルの模倣をしつつ、自分の色を加え独創性を打ち出す
- パクる・・・オリジナルを模倣しているだけ
つまり「真似る」には模倣に加え、「自分の色を出す」という一手間が加わっていますが、パクリにはそれがありません。
また、実はこの「真似る」行為、はるか昔から重宝されてきており、有名な偉人や成功者の名言からも、その重要性を垣間見ることができます。
良い芸術家は真似をする。偉大な芸術家は盗む。
パブロ・ピカソ
参照元:Inquiry
学ぶとは、まねぶ、つまり真似をすることです。では、何を真似るかといえば、それは「型」です。しかし、型を知識として理解するだけでは、学びにはなりません。仕入れた知識を行動に移して自分の変化を実感し、血肉化したとき、人は初めて学ぶのです。
高原豪久(ユニ・チャーム社長)
参照元:名言DB
何か新しいスキルを身につける時、大きな仕事を成功させようとする時、まっさらな状態からスタートするようでは気が遠くなります。けれど、実は偉人らも最初から作り上げることはせず、既存のものを組み合わせて価値を生みだしたようです。
何も参考にせず、自分の頭の中の限られた知識や経験則に頼るだけでは、新しい発想は生まれませんし、いつか行き詰まってしまうでしょう。何事においても、真似をするということは非常に大切で合理的なことなのです。
真似るのが苦手な人によく見られる特徴

冒頭では、新しいスキルを身につける、新しいことを成し遂げるには、真似ることが大切であるということをお話ししました。ここで、改めて真似るのが苦手な人によく見られる特徴についてまとめてみました。当てはまる項目が多い方は要注意です。
真似ることを卑怯なことと思い込んでいる
真似ることが苦手な人は、総じて真似ることは卑怯なことと認識しています。真似ることは、効率的にスキルや知識を身につける手段の一つに過ぎません。問題なのは、そっくりそのまま真似をすることであって、最終的に真似をしたスキルや知識を自分なりに昇華すれば問題ないのです。
仕事を覚えるのに時間がかかる
有能な人の真似をせずに、とにかく自分流でやってみようと動く傾向にあります。自分のやりやすい方法で行った方が効率的と思い込んでいて、結果的に一つの仕事を習得するまでに人一倍時間がかかってしまうのです。
視野が狭い、自分なりのこだわりを持ちすぎている
真似ることを敬遠しているので、我流なままで一向に視野が広がりません。こだわりを持ちすぎて、アドバイスされても、「それは自分に向かないから」とすぐに断ってしまう傾向にあります。結果的に、どんどん自分流に傾いて視野狭窄になってしまうでしょう。
真似る技術を習得する5つのポイント

では、真似る技術を習得する上でどのようなポイントが大切になるのでしょうか?それは、以下の5つのポイントに集約されます。
常識にとらわれないようにする
真似るということは、つまり新しい価値観や考えを自分の中に取り込むということです。今持っている常識にとらわれると、なかなか新しい価値観や考えは取り込めません。まっさらな素直な気持ちで真似ることが大切です。
人の行動や考えを観察する眼を養う
真似る上で欠かせないのが真似るポイントを把握すること。把握するには、観察が欠かせません。真似をしたいと思う人のまばたき、呼吸、視線、クセなど細かい部分を徹底的に観察しましょう。観察眼を養うことで、自然と真似をした方が良いポイントを把握できるようになるでしょう。
行動量を増やす
真似する行為と関係がないように思えますが、実は非常に関連性が高いです。なぜなら、考えているだけでは真似る技術は上達しないからです。行動を重ねるからこそ、どんどん真似が上手くなるのです。真似るには、とにかく色んな方法を試して真似ができるように努力することが大切です。
様々なものや人を参考にする
一つのものや人よりも、いろんなものや人を「真似の対象」にしましょう。一つでも良いですが、複数のものや人を対象にした方がより多角的な視点、気付きを得られます。また、それぞれの良いところ悪いところも客観的に見ることができるでしょう。
真似だけでなく自分なりの色を加える
真似をすることができたら、自分なりの色を加えましょう。冒頭でも書いたように、ただ真似をするだけでは「模倣したもの」にとどまってしまいます。自分なりに昇華させて、初めて「真似る」ことができたといえるのです。
いかがでしたでしょうか。
たとえ有能な人であっても、最初は先輩や上司を徹底的に真似るところから始まり、そしてそこから得た知識や知恵を自分なりに咀嚼し、自分の血肉にしているのです。あなたも早速、身近にいる優秀な人を真似しできるビジネスマンを目指しましょう。ぜひ、参考にしてみてください。
<ライタープロフィール>
担当ライター:ryusuke
大手広告代理店にて、顧客である百貨店や出版社のリスティング広告運用を担当。その後独立、広告代理店で培ったSEOやデータ分析の知見を活かし、個人メディアを運営する傍らフリーのWebライターとして活動中。執筆テーマは、グルメ関連やビジネス関連など、その他様々な分野のコラムや解説を得意とします。
公式ブログ
公式フェイスブック
販促レポートは、特集記事や販売促進コラム、オフィスでの問題解決など、皆さんのビジネスに少しでも役立つ情報をお届け。編集長の弊社代表と様々な分野で活躍する若手ライター陣によって、2008年より地道に運営されております。
★このページを友達に伝えよう:
FOLLOW @pqnavi
LIKE @pqnavicom
このレポートに関連するノベルティ素材
|
定価: 卸値:45円 |
|
定価: 卸値:112円 |
|
<アウトレット売切廃盤> [鏡] マットスクエアミラー(S) ピンク 定価: 卸値:105円 |
★関連エントリー:
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【明大前・桜上水エリア編】
- もう誤解を生まない!正しく伝わるオンラインコミュニケーション
- 3分でわかる採用ブランディング!メリットや方法を考察
- ビジネスマン必見!仕事ができる電源カフェ10選【恵比寿エリア編】
- 教え上手になろう!伝わる教え方の重要ポイント5つ
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(実践編)
- 経営者必見!課題分析を効率化する考え方「MECE」とは?(基本編)
カテゴリ:<仕事術ハック> の一覧
[お探しの検索ワードはコチラですか?]
フェアトレードコットン | 知育玩具 | キッチンタイマー | 鉛筆削り | ウォッシュタオルギフト | 洗剤セット | ペーパーウエイト | 干支
検索メニュー
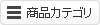


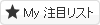
![ノベルティ:[鏡] コンパクトミラー](/img/item/Thumbnail21404G03.jpg)


![ノベルティ:[鏡] コンパクトミラー・ミニ](/img/item/Thumbnail390S06.jpg)
![ノベルティ:<アウトレット売切廃盤> [鏡] マットスクエアミラー(S)](/img/item/ThumbnailTM-0025-030.jpg)






